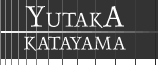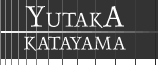企業論
(人間の繁栄について)
人間は神に近づこうとする動物である。神は無手段で生活が営まれ、かつ全能であるが、人間は手段を用いて生活しかつ全能に近づくことができる。江戸時代とほぼ同じ国土に現在は三倍もの人間が生活できていることも、また東京から九州や北海道へ行くのに現在ではたった一時間、昔の何百倍の速さで到達し得るのはジェット機という手段を用いるからである。神の瞬時にだいぶ近づいたと言わねばならない。
要するに私の言いたいことは、人間は神に近づく方向に進むことだけがその繁栄をもたらす所以であり、したがって、人類はより有効な財貨をより多く造り出し、それを使うことがその繁栄の道であると言わねばならない。
(企業のありかた)
したがって我々はより有効な財貨をより多く造り出す義務を背負っている。ところで合理性を追求する動物である人間はこの目的を達成する手段として、分業・協業という関係を作り、現在ではそれの具体的担い手が企業であり、その代表的なものが株式会社である。
したがって我々が会社で働くということは、そこにある建物、機械設備や器具を用いさらに人間関係に入るということで、換言すると人間が会社を使ってより有効な財貨をより多く作り出すことであり、そのような「場」が職場であり、会社であり、企業である。
このように、会社は各人の労働成果を偉大ならしめる手段であることからして当然人間が会社を使うという考え方が正しいのであって、今日のように「会社が人を使う」という考え方は主客を転倒している。この正しい考え方に立って初めて企業の公共性が理解でき、企業公器論の本質を見いだすことができるのである。
また神に近づく有効な財貨のより多くの造出と言うことは、自ら企業をしてより発展した手段として、しかも永続してその存続と成長を要請される。ここに企業を使役する者、すなわち従業員は、その企業の運用に当って成長発展をさす義務を有し、それを可能にするものが利潤であるから、企業を使役する者すなわち従業員は利潤をあげる義務を有す。ここにおいてまた、われわれは企業と利潤の公共性を見いだすのである。経営者が利益をあげることは、株主に対する責任だ、と言うが果たしてそんなものであろうか。
次にまた、企業はより有効な財貨を造り出すものでなければならない。このことは人間が絶えず進歩し、発展しようという意欲を持った動物であることから、当然社会的要請として、より優れた財貨を造出する義務を企業は有す。その創造的財貨の造出という要請に応えた企業がより利潤をあげることができ、発展することになる。ここにまた、企業および利潤の公共性を見いだす。したがって利益は大いにあげるべきものである。しかるに、最近世間に企業の利益はほどほどにして社会の利益を考えて経営を行うべきである、などと言うが、利益をほどほどにするとは、どの程度にすることなのか。そのような制度下にあって、果してほどほどにすることができるのか。出たい小便を途中で止めるようなものではなかろうかと私は思う。にもかかわらずそんなことを言わざるを得ないのは、企業に対する認識に根本的な誤りがあるからである。
|
|
企業と人間関係
(人間が会社を使う)
すでに述べたごとく人間が会社を使うのが正しい姿である。にもかかわらず今日では、会社が人を使うところに大きな過ちを犯している。
企業は本来利潤を追求するものである。前項までにのべたように、企業利潤は社会公共の利益とまったく合致するものである。しかるに資本主義社会における企業制度が私有制度と結びつき、誤った利益処分がなされるところに問題が起こる原因がある。すなわち企業が利益をあげるまではよいが利益が再投資に直接向けられないで、企業の所有者に帰属し、彼等はそれを任意に処分――――特に不都合なのは非生産的に用いること――――ができることである。
本来利益なるものは、その会社の所有者やある一部の人びとの所有に帰すべきものではない。利益はその会社に従事した全員のものであり、またその会社をとりまくすべての人びとに帰されるべきものである。その帰し方は、いわゆる再投資としてその会社の発展成長のために使われるべきである。しかるに一部の人びとが恣意的に処分し、また処分してよいという社会制度に誤りがある。その誤りに対して我々の抱く感情が、利益という言葉に反感として現われるのである。その反感を包蔵した利益をあげるためにある人ないし人びとが企業を起し経営する。そのためには人間を労働力という商品として、原材料や機械設備と同格の立場にして買い求め、これを使う。これに経費を加えたものがコストであるから、利益をあげるためには当然コストである人件費は引き下げねばならない。すなわち、安い賃金で買い入れようとする。これに対して労働者は企業や経営がどうであるかにかかわらず、その売値である賃金が妻や子、すなわち自分を含めた家族の物的面における人間として向上し、繁栄しようとするその生活の最大収入源であるから、最高の値段で売りたいのは最も強い基本的欲望である。その感情を秘めて、労働力の売買すなわち人間の売買が行われる。
どんなにきれいな言葉をもってしても、また経営内にどんな立派な施設をしても、このことを否定することはできない。奴隷を解放し売春を禁止した今日、白昼堂々と人間の売買が行われてよいものだろうか。私はこのことを思うとき、思わず目を覆い悪寒さえ覚える。
さて、その取引になると、安く買いたい、高く売りたい。ところが売る方は通常弱いから、意に反して安く売らざるを得ない。力が弱いからだ。そこで力の補強すなわち労働組合を作ってその力で交渉となる。買う方も当然また力の補強を図る。これが全国的な力の団体に発展して、片や総評や全労であり、片や日経連である。これらはいずれも力の団体であることをよく認識しなければならない。
かくて賃金は力ないよって闘い取るものとなり、経営をして敵味方の相対立する場とする。しかも賃金が自己の労働能力やその発揮とは離れて決り、さらに職場さえ離れて、はるか彼方で決るとすれば、さらにまた自己の労働成果と自己の取得する賃金となんら関係のないものであるとき、何をもって人間的労働の、その動機づけとすることができるであろうか。加えて自分達がより働いて上がった利益、それは反感のあるものだし、敵のものである。そこには使用者は監督に大きな目をもってし、労働者はサボルという卑屈をもってこれに報いる。それで愛社精神を説いたり、ヒューマン・リレーションズを云々してみたところで慰めにもなるまい。
かくて本来は人間の労働成果をより偉大ならしめるために存在する経営も、その成果が半減され、財貨の造出がブレーキされ、幸福であるべき人間が貧困への道を歩まされざるを得ないのである。
(企業参加の権利と受け入れ義務)
すでにみたごとく、人間の繁栄は、より有効な財貨をより多く造り出すことであった。したがって我々はより多くの財貨を造り出す義務を背負っており、この義務を果すために、すでに存在する職場や会社を使う権利を有す。なぜならもし企業が後輩の受け入れを拒み、あるいは企業に参加せずして財貨の造出をしたとしたら、人類は滅亡に近い打撃を被るであろう。すなわち先輩は後輩を迎え入れることが自分達の利益であり、後輩は先輩となってこれを繰り返すことによって人類の繁栄の生命が湧くのである。といって無秩序に受入れるべきではない。すなわち、その会社や職場に従事している人びと(新参加者を含めて)の労働成果を最大限にあげることを維持する範囲内においてなされるべきであり、さらにまた、より発展成長を願う義務がある以上より優秀なあるいはより適切な人材を選んで差支えないし、選ぶことによって人類は向上するのであれば、むしろ選ぶべきである。
(指導する、受けるの関係)
労働力を売買する企業においては、「使う」、「使われる」の関係が成立し、他人の考えによって自分の肉体が動かされる。動かされる人間にも考えや複雑な精神がある。そのやり場がないところに、人間は人間が使えない理由がある。
人間の労働成果の最も好ましい状態は、自己の労働意欲が自己によって動機づけられ、肉体とその精神とが一致して、組織づけられた目的に、むだとむらなく発揮されたときである。このことからして、後輩もまた使われてはならないと同時に、先輩や熟練者から、精神的にも、肉体的にも、また技術的にも指導を受けるべきである。先輩は後輩に教えることを快く感ずる。なぜなら先輩もまた利益するからであり、人類繁栄への本能としてもである。また、後輩もさらに同様の理由によって喜んで指導を受ける。受けて向上した成果のほとんどが自己のものになるときは、なおさらである。
こういう関係において初めて無理のない秩序が得られる。
(人間関係)
人間は神に近づこうとする動物である。
したがってその方向に進むことを進歩といい、その道程を成長発展ということができる。すなわち、何人も自己の成長発展を望む動物である。換言すると、より有効な生活手段である財貨をより多く駆使して全能に近づこうとしている。それがためには、そのような財貨をより多く造り出さねばならない。造り出すためにはより優れた能力を必要とする。しかして神に近づこうとする本能は、能力を向上させようとする本能であり、向上した能力を発揮しようとする本能である。そうして得た財貨を使おうとするものが人間である。
したがって会社において人間の労働に対する「動機づけ」はこのことを基本として出発し、そこへ還るものでなければならない。したがって私は職場や企業はこの基本のことが最もよく達成できる状態になければならないし、そうした企業が最も優れた企業であり、また優れた企業になると確信している。
この原則からしての具体的事例をあげると、まず能力が充分発揮できる場であること。そのためには適材適所の原則が貫かれていること。派閥やえこひいきがなく、学歴や偏見によらず実力(広い意味ですなわち種々な能力や人柄も含め)を向上し、自己の能力を伸ばそうとすれば伸ばし得る社内関係の確立。例えば当社においては、伸ばした能力が発揮できる職務が用意されそこに自ずと社内登用とスカウトとの基準が社内何人にも判り、波は立たない。また先輩は後輩をどれだけ伸ばしたか、その課をどれだけレベルアップしたか、あるいはどんな逸材を育てたかがその上司の重要な職務として評価され、自己を追起する後輩によって上司はなんら不利な影響を受けることなく、それどころかかえってその能力を高く評価されるのである。そして全体の向上がすなわち自分の利益になる関係の理解と実行。
かくてより多くの財貨の造出、社会への給付、それにバランスした自己の所得すなわちやればやっただけのことがある関係(このことについては次項で述べる)、それは、社外に利益が逃避しない原則と、各人の成果評価が公平に行われること。また企業所得の一部が再投資され我々の将来が安定発展的であるとの予測が立つこと。
次にまた我々は造出した財貨を使わねばならない。そのためにはより所得が多くなければならないこと、と同時にその時間が必要である。ここに労働時間短縮の意義がある。すなわち所得の増加に見合った余暇の造出を考えねばならない。
次に少々形而上の問題に触れねばならない。見えないことが、実は見えることより重要、少なくとも同じ程度において重要だから。
まず我々は人間であること、すなわち精神を持っていること、このことが他人を使い得ない最大の理由である。すなわち人間は自分以外の人格を使うことはできない。しかるに今日ほとんどの人びとが、使用者がいて他の労働者を使っていると思い、そのような関係づけにおいて社会が編成されている。ために図り知れない罪を人間は犯している。その最大なものが貧乏である。当社に「使う」、「使われる」の関係のない理由はここにある。人間には能力があり、企業はあくまでもその能力が充分発揮できるように関係づけされたものでなければならない。そのことが理解されるなら、人間が造った機械が幾ら進歩しようと、具体的に工場の作業組織において人間が機械の隷属的存在になる等という考えが起きたり、そのような作業を人間が行ったりすることはない。すなわち人間は作業の支配者であり機械の主人公である。人間は自分自身を変化させることができる動物である。と同時に自己の環境や外界を変化させる能力を持った唯一のものである。この本性にのっとった行動が人間の労働でなければならない。
したがってまた、機会と人間との関係がそうであるように、企業と人間の関係も、企業に一つの強い人格を与えて労働者をこれに隷属せしめる考え方は誤っている。また、企業内に各種の福祉施設を持ち、個人生活の領域にまで関係や支配を試みる等は、理解されるべきことではない。
|
|
成果配分
(自己の労働成果は自己が取得す)
あらゆる企業や経営の問題の中で労働成果、すなわち企業成果の分配の問題くらい重要なものは他にない。成果分配は企業の目的でなければならない。企業の存在はその成果分配を増大ならしめるための手段にすぎない。しかるに経営学者や識者の間において、企業は一度造られるとあたかも人格をもちそれ自体一つの生命体として考え、自ら成長発展すべきもののように論じられ、実務家もまたこれに組し「会社の発展のために・・・・・・」と言うがごときは「お家大事」の封建思想の残骸と言うも、それ以前の問題といわねばならない。
成果分配の増大が我々の労働目的であるから、当然我々の目的は労働した成果が良かったか、悪かったかが最大の関心事であり、目的の達成、すなわち自己の所得が自己の労働成果どおりにあがったか、あがらなかったかが関心の全部である。換言すると人間は自己の労働成果は自己が取得するのが原則であり、それを増大することが関心の全部である。そのために企業に参加して働いたのであるから、したがって経営の合理化も生産性の増大もすべてはそのためになされるべきものである。
にもかかわらずその成果が他人のものになったり、合理化も生産性の向上も、他人の利益の所得になったりするものに、人間は人格をもって協力することはできない。誤った経営においては、人間の労働は人件費とされ、それは原材料や、経費と同格であり、コストの一部にすぎず、したがって人件費である分配は減圧されることが好ましい、という考えになってくる。そして売上とコストの差額、すなわち利潤の増大の獲得が企業目的であり、その利潤は労働者とは関係のない人びとに帰属される仕組下にあって、労働意欲が起きるだろうか。それでも労働させるために人間の恐怖心を刺激して労働せしめる。ここでは人間は無視され、経営の幾つかの要素の中の一つにすぎず、本来の人間目的に目かくしをしたものといわねばならない。すなわち没目的な労働と言わねばならない。静かに目をつむって考えるがいい。自分がその労働を目的なく強制されるとき、どれだけの成果があがったのか、自分は一体何をしたのか、しているのか、それがわからない。自分の労働成果と自分の収入とが関係のないとき、自身が一生懸命にしかも継続して働くことが果してできるだろうか。その答は何人も「ノー」に決っている。しかるにそれを承知しながら現在それを人に強いているとしたらどうするべきか。自分一人の力ではどうにもならないというのか。それとも今日の企業や経営においては利潤だけ追求してないと言うか。そうなら何を追及しているのか。労働者に払う給料でいっぱいだとか、福祉施設をしているじゃないかなどと言っても言訳になるまい。
(給付と反対給付は均衡すべきである)
私はある人が社会に提供した価値量と、その人がそれによって受取るべき価値量とは均衡すべきであると思う。しかしてこの際言う価値とは使用価値ではなく、交換価値を指す。だからある年にその人が社会に提供したある商品によって受けた収入が百万円であって、その翌年、それと同じ商品を同一量提供しても、その収入が八十万円であることはなんら不思議ではない。
企業外における各人の所得はこの交換価値によって決められ、100を提供した人は100を受け、80であっても、120であってもならない。もし、80や120を受けるなら必ず何かによって100に引上げ、また引下げられる。
だから我々はより交換価値の高いものを社会に提供することが重要なこととなる。しかしてより交換価値の高いものは、原則としてより人類の進歩に貢献する財貨ないしサービスである。人間としてより神に近づける財貨を創造することである。企業における新商品の開発がより多くの利潤をもたらす最大の決め手であると考えられるのはこの故である。企業内において我々の所得は企業が交換によって得た反対給付の再分配であるから、我々の収入はその属する企業をしてより交換価値の高いものの造出を常にはかるよう総意を結集することが、第一である。次いで、入った給付の分配が公平に行われることである。何をもって公平とするか、今日の人間は、なおその絶対に公平である分配の決め手を持っていない。当社もまたそうであるが、今日の人間として考えられるうち、最も公平と思われる方法をとる以外にない。
(分配方法論)
通常、企業における分配はコストとしての人件費であり、申すまでもなく目的は利潤の追求である。したがって、一例を示すと、総売上高を百として、利潤が十%、経費二十五%、人件費二十五%、原材料費四十%となるが、私の考える経営においては、総売上高を百として、分配25%、再投資10%、経費25%、原材料費40%となる。さて単に右のとおりなら、従来の経営とほとんど異ならない。利潤が社外に逃亡しないことと、人件費を分配と言い換えたにすぎない。
ところが実際はどうか。総売上高を100として、分配35%、再投資15%、経費20%、原材料費30%となる。このように変化する理由はここまでお読みくださった読者にはすでにおわかりと思う。
ところで他社と異なる点は、当社における原価(コスト)とは原材料費プラス経費であること、利潤とか利益がないこと。したがって利益の社外流出がないのみならず留保され、資本増加に役立ち、しかも配当や利息を伴わないのを原則とする再投資分と、人件費に代わって企業目的である分配勘定となることである。したがって分配勘定以外の再投資分、経費、原材料費をどう操作するか、もって総売上をいかに伸ばすかを考え、結果として分配額の絶対額増加を狙うのが当社である。
次に社内分配の方法は、人間は何人も生存する権利を有し、人間である理由によって強い者、能力のあるものが、そうでない者を援助する義務を有すると考えて基本分配額を設け、その製品を換金するまでに各人の貢献した度合、すなわち職務評価、成果評価、貢献度指数、チームワークに対する人格評価などにより、職能分配額と利益分配額を設ける。以上三つの要素に大別される。
|
|
企業内人間組織の原則
(人間と幸福について)
神は人間に幸福を与えていない。与えたものは幸福が来るかのごとき錯覚である。
その幸福とは、安心立命とか、足るを知るとか、無欲の境地とかいったものを指す。そのような幸福を、人間の歴史が始まって以来何人か得た人がいるだろうか。もし得た人がおり、そのような人が増えたとしたら、人間は衰亡の歴史を作らざるを得ないだろう。だから私はそのような幸福を求めることは罪悪だと思う。
人間は欲をたくさん持ち、いつも不足感に埋まり、無限の欲求、すなわち人間が福に近づく永遠の道程を歩むこと、そこには常に問題を作り、それと四ツに組んで解決していく過程が人間の姿であると思う。だから人間が一番なさねばならないことは能力の向上である。強いて幸福という言葉を使うとするなら人間の幸福は自己の能力が向上している姿を自他共に観ることであり、その成果としてのより進歩した物的(サービスを含む)生活手段をより多く使用することができ、もって神へより近づきつつあるときに幸福はあると私は思う。
したがって企業においては、各人が労働能力を向上させていき、しかもそれを自分で意識できる状態のときが幸福な状態といわねばならない。だから企業組織はそれが一番よく達成できるようになっていなければならない。
第二は競争と調和の原則である。人間は常に他の人と競争しようとする本能をもっており、この本能が労働を通じて適当に昇華される組織であること。反面また、他人と握手しようとする本能を持っている。両輪がうまく組織に活かされることが肝要である。
第三は適材適所の原則である。能力は一様ではない。求める能力も多様である。社会も複雑である。これが造化の神の妙である。その能力を適所に導き発揮できるなら神の意に沿い得たものといえる。ただ適材の発見も、適所への配置も考えるべくして容易のことではない。それほど人間の能力は微妙である。第一本人自身が、自己の優れた能力さえ容易に識ることができないのである。
第四は成果の認識と給付の原則である。人間は自己の労働成果を認識したいと思っている。それによって達成欲を満足させ、自己の能力の成長を識ることができる。さらに自分の造った部品が完成品のどの部分でどんな機能を果しているか、またその労働成果が企業成果にどのように役立ち、それを通じて自分が社会にどんな役割りや貢献をしているのか、さらに自己の所得との関連が各人にわかると同時にそれに見合った反対給付があるような組織や状態を造り出すこと。
特に重要なことは人間能力の成長という成果の評定と認識の方法に関することである。もし、人間の創造能力の発揮を促し、それを正当に評価することに成功するなら、その企業の繁栄は保証されるだろう。
第五は人間の特性を発現し得る組織であること。人間の特性とは、想像、予測、判断、調整、統合するといった能力を持っていることである。このことが人間は他の人間を使うことのできない所以であり、すでに述べたように人格はその所有者しか使うことができないものであるから、我々が自主的に働く意志が起きる組織であり環境であり、社風でなければならない。私の考えるところでは、人格を労働力として売買する、したがって「使うもの」「使われるもの」という関係化にあっては解決できないと思う。人間のそれらの特性が自主的に働く意志の起きる環境下にあって、充分発揮できるような作業組織であり、生産組織であり、指導組織(他では管理組織)であること。
|
|
利益なき繁栄
(再投資の必要性)
我々は人類の繁栄の生命の中に自己の生命を見出したときいわゆる幸福である。言換えると安定的発展を望むものであるということである。それを最も具体的に意識し得るのは自分が参加して企業が発展し成長している場合である。すなわち我々は自己の繁栄を望むなら自己の所得を増加させると同時に、参加している企業をよりその目的に添った状態に発展、成長せしめることが、自己の所得を増加せしめる所以である。具体的にはすでに述べたように企業所得の一部を再投資に向け、企業が発展すればするほどより後輩を受け入れられ、先輩はより価値の高い職務に就くチャンスが予測でき、特に社内登用主義と相まって、各人は自己の能力の成長を図れば、その能力が発揮できる椅子が待っている。したがってまた自己の所得を増加せしめることができ、生涯の安定と幸福が予測できるのである。この循環過程が人類繁栄の生命の実相と思う。
また江戸時代と今日、日本では約3倍の人々が生存していること、さらに生活程度が仮に2倍上昇(実際は比較し得ない)したとすれば、すなわち六倍の財貨の造出を我々の先輩が図ってきたから今日一億近い人間が生活し得ている。と同時に我々の先輩が企業、すなわち職場を発展してきてくれたから今年学校を卒業した人々がまた職場に参加することができる。だから我々人間はその労働成果を偉大にするために企業に参加する権利を有する。また後輩は先輩となってその職場をより発展せしめてさらに後輩を迎え入れる義務を有す。と同時にすでにみたいようにそうすることが先輩の生涯の発展の歴史たらしめる所以であり、利益であることも知った。企業とはそのようなもので、是すなわちまた公器である所以でもある。
このように利益はその企業に参加している人々の将来の安定発展に再投資されるべきものであるにもかかわらず、企業内において全く関連のないことにも恣意的に処分されるところに、労働者は搾取ないし横取りされたと考え、利益に対する反感となるのである。
|
|
利益の源泉
利益の源泉は労働力にある。しからば労働すれば必ず利益はあるか、そうはいかない。企業の利益は取得した価値に労働を加え、造出した附加価値分が交換価値分として転移したときに生ずるのが原則である。がこれとて余りにも例外の多すぎる原則であって、妥当性も普遍性も欠く。したがって企業の利益は企業が原材料として所得した、すなわち交換価値量とそれに加えた労働力によってできた新たな価値が、交換価値に転移したときに生ずるか否かが決定する、といわねばならない。
したがって余剰価値は労働力の搾取から生ずるものではなく、使用価値が交換価値に転移したときに生ずるもので、その転移によって生ずる余剰価値とは、人間が進歩発展に必要なより有効な財貨に対し認めた価値、人類をより万能に近づける効用に対する価値、その商品によって現われた人類の繁栄のために最も重要な創造的価値に対する価値、といったこれ等の価値が交換価値として具現したとき、その根源となった諸価値量の合計との差である。したがって企業が利益をあげ、その参加者の所得を増大せしめかつ企業が発展成長していくためには、人類のより発展に貢献する財貨の提供を図ることが何よりも重要といわねばならない。このように考えて初めて最近言う先発利益を狙えとか、新製品の開発とか、積極的市場の開拓とかいう意義が理解される。
かくして得られた企業利潤が、さらに新たな財貨造出のためにダイレクトに投資されるとき、企業には利益なき繁栄がもたらされる。
|